新式2号
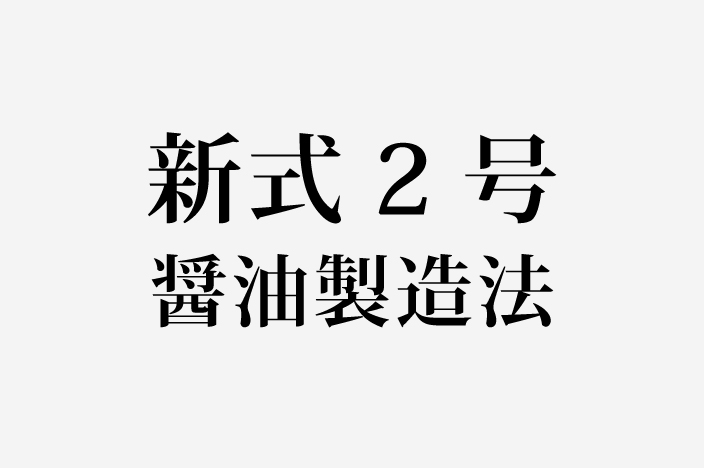
新式2号醤油製造法
1948年(昭和23年)、キッコーマンの研究員である舘野正淳、梅田勇雄らによって発明された醤油の製造方法。たんぱく原料(脱脂加工大豆など)を希塩酸で分解中和したものに、小麦などからつくった麹を加えて50日前後発酵熟成を行う。
半化学、半醸造による醤油の製造法
希塩酸で化学的にたんぱく原料をペプチド程度まで分解し、その後は麹の酵素によってアミノ酸まで分解させるという、半化学、半醸造による醤油の製造法で、窒素利用率を60%から80%程度に高めることができました。
実は、この技術が開発され、キッコーマンが特許を無償公開したことが、現代の醤油醸造技術につながっているということもできます。
現代に続く醤油業界を守った技術
1948年にGHQは2万トンの大豆ミールを放出する方針を示したのですが、醤油業界:アミノ酸業界=2:8の比率で供給するとしていました。
醤油は原料から製品になるまでに1年という長い時間をかけても、原料に含まれるたんぱく質の60%しか有効利用されず、40%は醤油粕になってしまうことで、効率が悪すぎるという理由だったそうです。
このままでは原料が十分に供給されずに醤油業界の存続も危ぶまれた状況で、新式2号醤油製造法が生まれたことにより、大豆ミールの供給量が7:3で醤油業界に提供されることになったそうです。この技術が現代の混合醸造方式につながってきているということもできると思います。
戦時中の醤油
https://s-shoyu.com/knowledge/0604/
キッコーマン「新式2号醤油製造法」と特許無償公開について
https://www.kikkoman.com/jp/quality/ip/topics2.html


