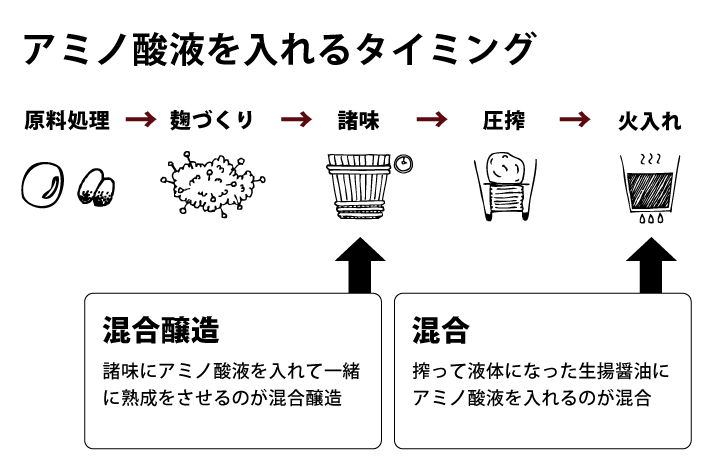下り醤油
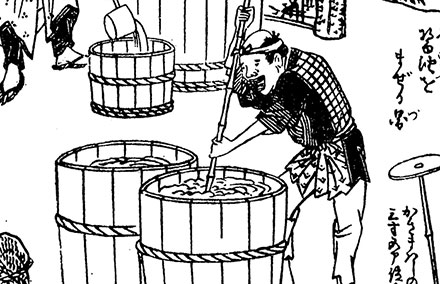
「くだらない」の由来
「くだらない」という言葉は現代でも使われますが、これは江戸時代の物流が語源になっているようですね。江戸のはじまりは、田舎の土地の開拓からはじまっているので、当時は、京都や大坂から江戸へ運ばれた品は品質が高く、「下ってくる」ため「下りもの」と称され、逆に、それに当てはまらないものが現代の「下らない」=品質が劣る、という意味の語源になったと言われています。
「下り酒」などと同じように「下り醤油」という表現もあったようで、それは西日本でつくられて江戸に運ばれてきた醤油を指します。本格的に醤油が生産されるようになったのは江戸時代で、1726年の「下り醤油」は約76%を占めていたといいます。
江戸産の醤油の盛り返し
そして、次第に千葉県を中心とした関東の醤油の品質が向上します。1821年の醤油問屋の上申書によると125万樽のうち下り醤油はわずか2万樽、つまり、ほとんどが関東産になっています。
当時の「下り醤油」は溜醤油に近いものと推測されて、大豆が主原料だった醤油に、ヒゲタ醤油の第五代の田中玄蕃が小麦を原料に使ったとの記録が残っています。現在の濃口醤油の製造法のスタートで、江戸の人が好む醤油を開発して品質と生産量を高めていったという背景があるように思います。
田中玄蕃(ヒゲタ醤油・玄蕃蔵物語)
「田中 玄蕃」から始まったヒゲタしょうゆの醸造
https://www.higeta.co.jp/enjoys/tenchijin/genbagura/